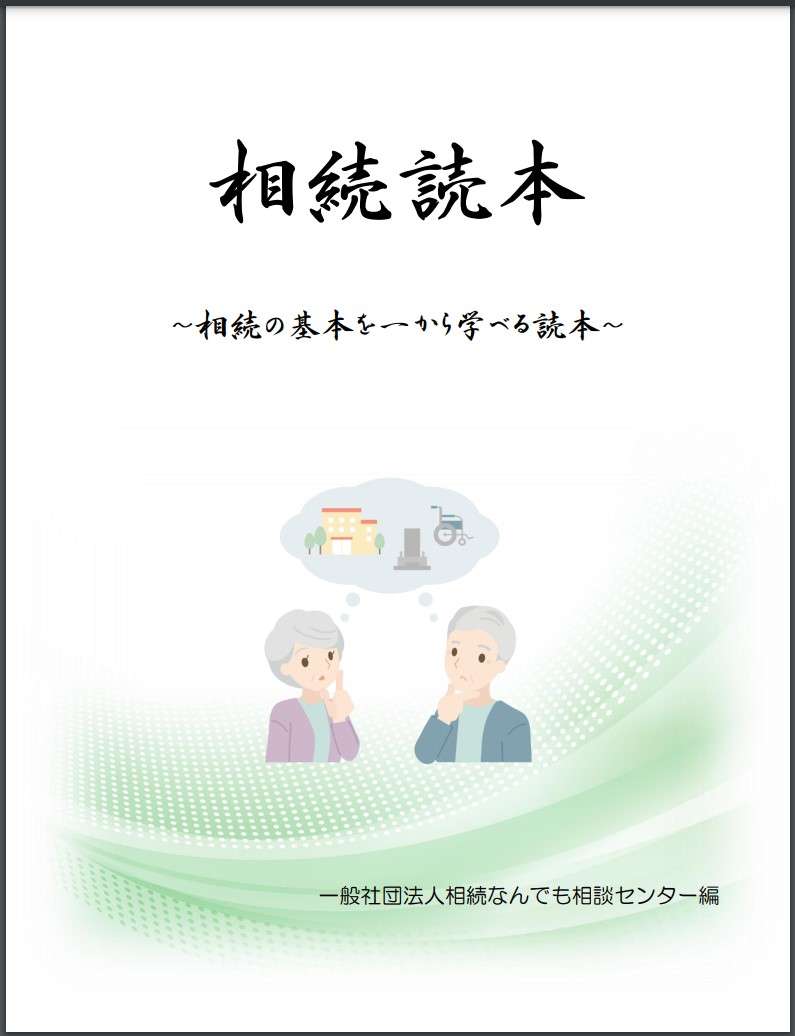【相続】不動産を相続する際に関わる法律には何があるのか
2022/12/12
目次
【相続での不動産に関わる法律とは?】
不動産を相続する際にも様々な法律が関わりますが、相続の大元となるのは民法です。そこでこのレポートでは民法の内容を見ておきます。
そして、この民法は令和2年(2020年)に法改正があり、相続に関係する部分(一般的には相続法と言われます)についても、約40年ぶりに改正されました。
改正された内容を知っておかないと、いざ相続するとなったときに、慌ててしまったり、よくわからないまま相続人同士で話し合いをして遺産分割協議書にハンコを押してしまったり、結果的に損をしてしまったり、などということになってしまう可能性がありますので、しっかり理解しておきましょう。
以下では、改正された中で、特に大切な改正点を6つ取り上げます。
【相続に関する民法改正で特に大切な改正点6つのポイント】
民法改正で特に大切な改正点6つのポイントをカテゴリーごとに説明します。
【①配偶者居住権の新設】
配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人といいます)の配偶者が、相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた場合に、その配偶者が建物の所有権を相続しなくても、代わりに「配偶者居住権」を取得することにより、そのあとの生涯又は一定期間、その建物に住むことができるという権利です。
なぜこの「配偶者居住権」ができたかというと、これまでの民法の規定では、例えばご主人名義の建物に長年夫婦で住んで生活していたが、ご主人が亡くなって相続が発生した場合に、奥様がその建物を相続で取得しなければ、奥様はその建物で生活することができなくなるという可能性があったのです。
具体的な事例で考えてみます。
ある夫婦が、ご主人名義の土地建物の一戸建ての自宅で、長年暮らしていました。2人の間には1人息子の長男がいますが、すでに結婚して両親とは違う場所に住んでいます。
その後、ご主人が亡くなりました。ご主人は遺言書を書いていませんでした。ご主人の財産は一戸建ての自宅と預貯金です。自宅の評価額は2,000万円、預貯金は3,000万円ありました。
このような場合、ご主人に遺言書が無く相続が発生すると、相続人である奥様と長男との間で、「遺産分割協議書」という相続の分け方についての話し合いを行わなければなりません。
なお、奥様には2分の1の法定相続分があり、遺産分割協議書では、相続人自らが持っている法定相続分を主張することができます。
通常の、世の中によくある話し合いであれば、この場合の長男も、母親である奥様が自宅を相続し、預貯金も奥様が相続することに同意することになるのでしょうが、万が一話し合いが難航すると、大変なことになってしまいます。
すなわち、ご主人の財産は、自宅2,000万円と預貯金3,000万円の計5,000万円であり、長男から自らの法定相続分を「満額」主張されてしまうと、奥様の取得分は2,500万円、長男の取得分は2,500万円となります。
その上で、奥様が住むために自宅を相続すると、預貯金はそのほとんどが長男に渡ることになるため、奥様はいずれ生活できなくなる可能性があります。反対に奥様が生活するために預貯金をすべて相続すると、自宅は長男に譲るため、奥様は住む場所に困る可能性があります。
このような不具合を解消するために新設されたのが「配偶者居住権」です。これにより奥様は配偶者居住権をもとに自宅に住み続けることができ、生活資金も確保することができます。
先の場合で仮に配偶者居住権の価値を1000万円とすると、奥様は預貯金を最低でも1500万円取得することができます。
長男は配偶者居住権の負担のついた土地(尚、評価額は土地評価額から配偶者居住権評価額を差し引いたものとなります)と預貯金の残りを相続することになります。
そしてそのあと、奥様が亡くなると、配偶者居住権は無くなる(居住者である「配偶者」が亡くなるからです)ので、ご主人の相続で自宅の所有権を相続した長男は、配偶者居住権の負担が取れた完全な所有権を取得し、自宅の完全な所有者になります。
また、配偶者居住権はその配偶者が亡くなると消滅する(=価値が無くなる)ため、配偶者が亡くなったときに生じる相続(一般的に二次相続といわれます)において、配偶者居住権を設定していなかった場合に比べて、相続税の負担が軽くなることも場合によっては生じるのです。
この配偶者居住権は、遺産分割協議で協議し取得することができる他、被相続人が遺言書で配偶者に遺贈などさせる旨を記載し、その遺言書に基づいて取得することもできます。
ただし、配偶者居住権は売却などができない他、所有者と居住者それぞれに権利を持たせることから、将来的に不具合が生じる可能性もあります。
そのため、配偶者居住権の設定や遺贈については、前に専門家へ相談することをお勧めします。
【②居住用不動産の贈与等に関する特例措置】
居住用不動産の贈与等に関する特例措置とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産の遺贈または贈与がされた場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定され、原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えることになる措置をいいます。
一般的に居住用不動産を生前に贈与した場合、これも「生前贈与」といいますが、生前贈与があると法律上「特別受益」があったものとされ、これをいわば遺産の前渡しがあったものとして、そのあと贈与した人が他界して相続が発生し遺産分割を行う際に、贈与された人はその生前贈与された分を含めて相続財産を取得する、すなわち本来相続できる分から生前贈与分が差し引かれることになります。
具体的な事例で考えてみましょう。
あるご夫婦が一戸建てを建てて、土地建物共にご主人名義とした上で、家族で生活していました。ご家族はご夫婦と長男、長女です。そのあと、長男、長女とそれぞれ結婚して別世帯で生活を始めたため、ご夫婦二人、仲よく一戸建てで生活していました。
ご主人は、いずれ自分の方が先に旅立つだろうからと、そのあとの奥様の生活を案じ、先に一戸建ての自分の持ち分の内、2分の1の評価額2,000万円を奥様に贈与しました(生前贈与です)。
そのあと、ご主人が亡くなりました。ご主人は遺言書を書いていませんでした。ご主人の財産、すなわち遺産は、一戸建ての残る持ち分2分の1の評価額2,000万円、あとは預貯金及び株券の評価額計6,000万円で、その合計額は8,000万円でした。
ご主人に遺言書がありませんでしたので、奥様、長男、長女の3名で遺産分割協議を行うことになります。奥様の法定相続分は2分の1ですが、それに基づく遺産の取り分を計算する際、生前贈与があった場合にはその分も遺産に含めて計算することになるのです。
すなわちこのケースで、奥様の取り分を計算する際には、遺産8,000万円に生前贈与2,000万円を加えたものに対して2分の1を掛け合わせて得られた額5,000万円から生前贈与分2,000万円を差し引いて得られた額の3,000万円となり、遺産分割協議で法定相続分に基づいて取得する場合の遺産は3,000万円、これに生前贈与2,000万円を足し合わせると、最終的な取得額は5,000万円となります。
しかし、これでは仮に生前贈与が無かった場合における、遺産分割協議で法定相続分に基づいて取得する場合の額と差異が無くなってしまいます。
なお、この場合で奥様の取り分を計算する際に生前贈与分を遺産に含めることを「持ち戻し」といい、この持ち戻しを行わないこととすることも法律上は可能なのですが、そのためにはご主人が遺言書などで「持ち戻し免除の意思表示」をすることが必要であり、この場合では遺言書が作られていなかったため、従来この場合では持ち戻し免除を行うことができなかったのです。
このような不具合を解消するために、今回の法改正で創設されたのが居住用不動産の贈与等に関する特例措置です。先に述べた通り婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産の遺贈または贈与がされた場合、仮に遺言書などで持ち戻し免除の意思表示がなされていなくても、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
なぜこのような措置が作られたかというと、長年一緒に生活を営んできた夫婦の元では、その居住用不動産はいわば長い期間にわたって夫婦で協力し合いながら作られた財産であり、この場合で生前贈与したご主人としては、持ち戻しをさせないという意思があったであろうと考えるのが合理的であるという趣旨なのです。
そしてこの場合で奥様の取り分は、遺産8,000万円に対して2分の1を掛け合わせて得られた額4,000万円に生前贈与2,000万円を足し合わせた6,000万円となり、仮に生前贈与が無かった場合における法定相続分に基づいた遺産取得額よりも多く得られることになるのです。
【③預貯金の払戻し制度】
預貯金の払戻し制度とは、遺産に預貯金が含まれる場合に、相続人は遺産分割協議が成立する前であっても、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるという制度です。
これまでは相続人が亡くなると、相続人名義の預貯金口座は凍結されてしまい、亡くなった方の葬儀費用や入院費用、入居費用などにその人の預貯金を充てることができず、家庭裁判所の許可が無い限り、相続人自らの資金にて支出しなければならないなど、不具合がありました。
なぜなら、以前最高裁で、預貯金も遺産分割の対象となるため相続人は単独で払戻しを受けることができないという判断が出されたためです。
このような不具合を解消するために今回の法改正で設けられたのが預貯金の払戻し制度です。これにより、亡くなった方の葬儀費用や入院費用入居費用などにその人の預貯金を充てることが可能となりました。
もっとも、相続人間の公平性を保つために、払い戻すことができる額には一定の範囲という限度が定められています。この一定の範囲とは、相続開始時の預貯金額に、自分の法定相続分を掛けて得られた額の3分の1までとなります。
お父様が他界し(なお、お母様はすでに亡くなっているものとします)、お父様にはある銀行に預金600万円の残高がありました。相続人は長男と次男であり、それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなります。
したがって、長男次男それぞれ、その預金600万円に自分の法定相続分を掛けて得られた額300万円の3分の1、すなわち100万円ずつを単独で払い戻すことができるのです。
なお、これを超える額の場合には、別途家庭裁判所に対して、仮に分割するための手続(仮分割の仮処分)が必要となります。
【④自筆証書遺言の要件緩和】
遺言書には、自分で作成する遺言書=自筆証書遺言、公証役場で作成してもらう遺言書=公正証書遺言、などがありますが、この中で自筆証書遺言は、自分一人で作成するため、誰にも知られずに作成することができ、また費用が掛からないなど簡単な方法です。
しかし、遺言書の全文を自筆で書く=自書が必要であったため、高齢者を中心に、作成することについてハードルの高さに困難を感じる方がいらっしゃいました。
このような不具合を解消するために、自筆証書遺言の作成に関して、要件が緩和されました。
具体的には、パソコンで遺産の目録を作成しプリントアウトしたものや、預貯金口座の通帳コピー、不動産の登記簿謄本などを自筆証書遺言に添付する形でも遺言書作成が可能となりました。なお、添付するものにはすべてのページに自署し押印する必要があります。
しかしながら、遺言書本文は依然として全文を自書する必要がありますので、書き方や修正方法などは、法律上の要件に基づく必要があります。
また、併せて自筆証書遺言の保管制度が設けられました。これは作成した自筆証書遺言を、全国にある法務局で保管できるというものです。これにより、自筆証書遺言を無くしてしまった、破損してしまった、というリスクを防ぐことができます。
加えて、相続開始後に必要な家庭裁判所での検認手続も不要となります。もっとも、法務局は単に「保管する」だけで、遺言書の内容の有効性などをチェックしてくれる訳ではありませんので注意が必要です。
【⑤遺留分制度の見直し】
今回の法改正で、遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
そもそも遺留分とは、相続が発生して遺言書があり、ある相続人が何も相続しないなどの場合であっても、その相続人が相続財産の中で最低限もらえる割合のことをいいます。
なぜ遺留分制度があるかというと、遺産が特定の人に集中して相続されることによる、他の相続人との不公平性を是正するためです。
例えば、お父様が亡くなり(なお、お母様はすでに他界しているものとします)、長男と長女が相続人であり、お父様が遺言書を作成している状況で、その遺言書に「すべての財産は長男に相続させる」と書かれている場合に、不公平な状態に置かれている長女に対して、遺留分を保障しているのです。
そして、遺留分は、亡くなった方の兄弟姉妹を除く相続人に存在し、その割合は各法定相続分の2分の1であり(したがって先の例での長女の遺留分は4分の1となります)、遺留分を請求するには、被相続人が亡くなったこと及び自らの遺留分が侵害されたことを知ったときから一年以内に、遺留分を侵害している人に対して権利を行使する必要があります。
これまでの法律では、遺留分を請求することを遺留分減殺請求といい、この遺留分減殺請求の権利を行使すると、請求をした人の持つ遺留分減殺されている割合に応じて、すべての遺産に対して共有となりましたが、実は弊害が生じる場合がありました。
具体例で説明します。
会社を経営していたお父様が他界し(なお、お母様はすでに亡くなっているものとします)、遺産として預金1,234万5,678円の他、会社の株式として評価額1億1,123万円の株がありました。相続人は長男と長女で、お父様は遺言書を作成していました。
その遺言書には、お父様の事業を手伝っていた長男に会社の株式をすべて相続させる旨と、長女に預金をすべて相続させる旨が書かれていましたが、その遺言書の内容に不満のある長女は、長男に対して遺留分減殺請求権を行使しました。
そして行使の結果、これまでの法律では、長女の遺留分(法定相続分2分の1に2分の1を乗じて得られた割合)が侵害されている割合に応じてすべての遺産に対して共有となることから、長女の遺留分が侵害されている額【計算式会社株式の評価額1億1,123万円+預金1,234万5,678円)×1/2×1/2-1,234万5,678円】=1,854万8,242円の分につき、会社株式は共有となってしまいます。これですと、株式を共有で持ち合うことになるため、円滑な会社経営に支障が生じる恐れがあるのです。
このような弊害を防止する観点から、今回の法改正で、これまでの遺留分減殺請求から、遺留分侵害額請求という金銭請求へと内容を改めました。このケースで遺留分を侵害された長女は、長男に対して、遺留分侵害額に相当する金銭である1,854万8,242円の支払請求をすることができるようになったのです。
これにより、遺留分を請求することで当然に生じていた遺産の共有関係の弊害を回避することができると共に、ある遺産を特定の人に引き継がせたいという遺言書を書いた人の意思をより尊重することができるのです。
なお、遺留分侵害額請求を受けた人が、その請求をした人に対して支払う金銭を直ちに準備することができない場合には、判所に対して支払期限の猶予を求めることができます。
【⑥特別の寄与制度】
今回の法改正で、ある人が亡くなった場合に、その亡くなった相続人以外の親族が、無償で亡くなった方の療養看護などを行い、その結果亡くなった方の財産の維持や増加があったと認められる場合には、亡くなった方の相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになりました。
そもそも寄与分とは、相続人の中に亡くなった人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合に、かかる貢献を考慮し、その人に対して特別に与えられる相続財産の持ち分をいいます。
寄与分として考慮されるには、その寄与が特別の寄与であると評価されるレベルでなければなりません。すなわち、亡くなった人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献が必要になるのです。例えば、親子間には相互扶助の義務がありますので、それを超えるレベルの貢献が必要となります。
また、特別の寄与であるか否かは、「絶対的に」判断されます。すなわち、亡くなった人に対して、ある方が他の相続人と比べてより貢献したというような「相対的な」ものではダメなのです。
そして、特別の寄与と評価されるには、寄与行為に対する対価や補償を受けていないこと(=寄与の無償性)、事業に関する労務提供や、亡くなった人への財産上の給付・療養看護等による、亡くなった人の財産の維持・増加への寄与が必要となります。
ただしこの寄与分は、これまで相続人についてのみ認められていました。そのため相続人に密接した立場の人間が、亡くなった人に対して特別の貢献をした場合でも、その貢献者は相続人ではない以上、寄与分が認められていなかったのです。
お父様が他界し(なお、お母様はすでに亡くなっているものとします)、その子として長男、次男、長女がおり、お父様は他界するまで長男とその妻と共に同居していました。そして長男夫妻には子供がいませんでした。また長男はお父様が他界する一年前にすでに亡くなっていました。
長男の妻は長男の生前からお父様の世話をしており、お父様が高齢になってからは、お父様の介護を献身的に行い、それまで勤めていたパートを辞めて、介護に集中し、昼も夜も無い状況であり、また長男の妻は一切報酬等を受け取っていませんでした。
そして介護の結果、お父様の財産は減少することなく維持されたこともあり、その介護は特別の貢献と評価される内容のものでした。
具体例で説明します。
お父様の相続が始まり、遺産分割協議でまとまらず、家庭裁判所で調停をすることになりましたが、長男の妻はお父様の相続人ではないため協議にも調停にも参加すらできず、長男も亡くなっており、子供もいないため、長男の妻は蚊帳の外です。
しかも、お父様に特別の貢献をしたにもかかわらず、長男の妻は相続人ではないため、寄与分を主張することもできませんでした。
このような不具合を是正するために今回の法改正で設けられたのが、この特別の寄与制度です。
このケースで長男の妻は相続人ではありませんが、無償でお父様の療養看護を行い、その結果お父様の財産の維持があったと認められますので、次男と長女に対して金銭の支払を請求することができるのです。
なお、長男の妻は婚姻により親族関係を取得しており、その親族関係は、長男が他界しても継続しますので、親族要件を充たしています。
これにより、長男の妻による介護の貢献に報いることができ、実質的な公平を図ることができるのです。
以上、相続に関する民法改正で特に大切な改正点六つのポイントを説明しました。なお、以上の他にも改正点は多くありますので、詳しくは弁護士や司法書士などの専門家に話を聞くことをお勧めします。
相続についてより詳しく学びたい方
この「相続読本」は相続なんでも相談センターが長年に渡って培った相続のノウハウが詰まった1冊です。何から始めていいかわからない方、何を調べて、何を勉強すればいいのかわからないでも必ずこの1冊の中に知りたいことが詰まっています。
是非一度、手に取ってみてください。こちらのページからダウンロードできます。