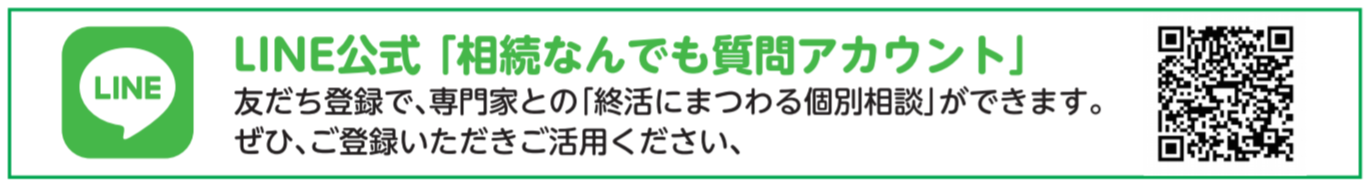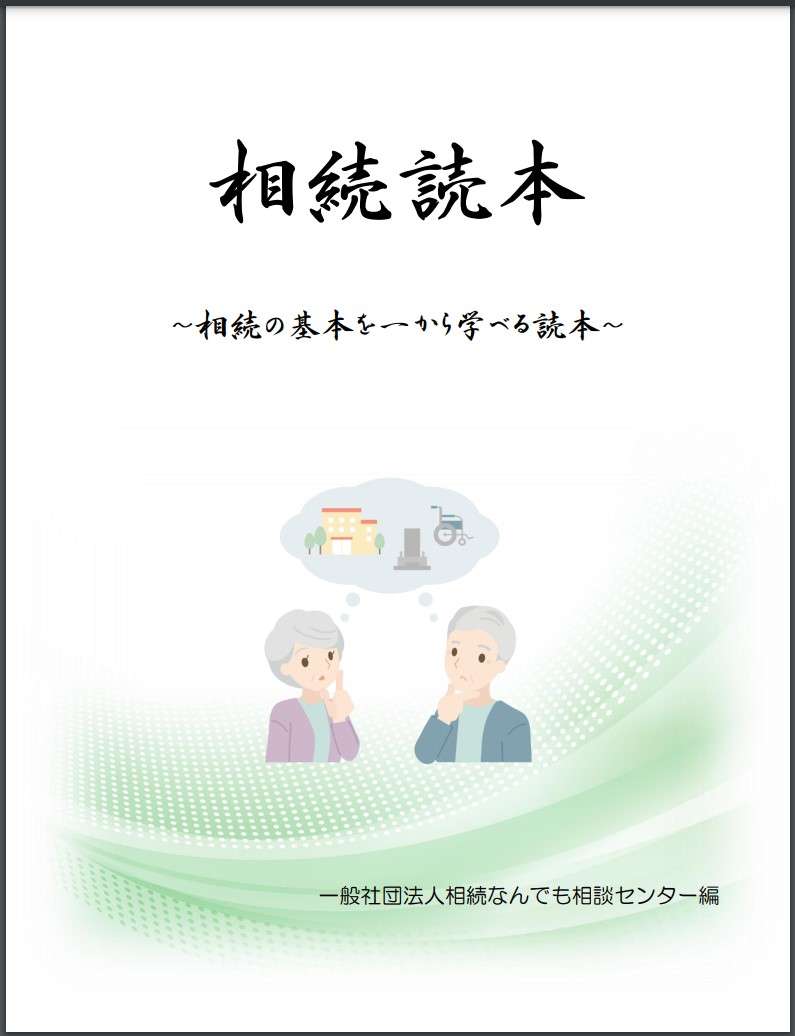遺言書書き方「遺言の遺言書の違い、遺言書作成、遺言書の効力、遺言種類」
2020/12/17
目次
【遺言書はなぜ作成するのか?】
なぜ、遺言書を作成するのか
人は生きている間、自分の財産をどのように処分するのかを自由に判断できるのが原則です。このような自分の財産に対する自由は、基本的に死後も認めるべきとも考えられます。
しかし、死後に自分の考えを示すことはできませんから、生前から死後の財産の処分についての考えを示しておくことが必要です。自分の仕事の財産処分に関する一定の考えを「遺言書」の形で示しておくことで、遺された親族間でのトラブルを防ぐことにもつながります。
なお、遺言書は、日常生活の中で遺書と呼ばれていますが、遺言書が民法の定める厳格な方式に従って作成し、法的な効力が備わった文書のみを指すのに対し、遺書は故人が遺した文書全般を指します。
【どんな場合に遺言書を作成するのか?】
遺言書は、遺言者(被相続人)がさまざまな目的から、自分の財産について、誰に対し、どのように分配して欲しいのかを明確にする手段として作成されます。尚、遺言書と似ている言葉として、「遺言」があります。
遺言書に書かれている故人の考えのことを遺言と言いますが、遺言書の意味で「遺言」を使うこともありますので、両者は同じ意味を持っていると考えて支障はないでしょう。
典型的な例が、自分の配偶者や子など、特定の人に多くの財産を遺したいという目的から、その特定の人に多くの財産を与えることを遺言書に明記しておく場合です。これにより、法定相続分にとらわれることなく、遺言者が希望した通りの財産の分配を実現することが可能になります。
次に、相続権がない人(内縁の配偶者、お世話になった人等)に財産を遺したいという目的がある場合です。この場合は、相続権がない人に財産を与える(遺贈にあたります)ことと、どのくらいの財産を与えたいのかを、遺言書の中で明記してくことが必要です。遺言書を作成しておかないと、相続権がない人に対し、自分の死後に財産を与えることができなくなるからです。
遺言者が自分の財産を与えるに際し、「結婚した時に財産を与える」という停止条件を付けたり、「ペットの面倒をみること」という負担をつけたい目的がある場合は、必ず遺言書の作成が必要です。
遺言書に停止条件や負担を明記しなければ、とくに停止条件や負担のない状態で、遺言者の死後に財産が承継されてしまいます。尚、条件の内容が成就した時に遺言の効力が生じるとするのが停止条件、財産を受け取る人に、一定の義務を与えるのが負担です。
さらに、遺言者が会社を設立せず、個人の立場で事業をしていた場合は、遺言書の中で後継者を指名することがあります。事業用の不動産や機械などは、個人事業のときは相続財産に含まれますので、法定相続分に従って分割されると、事業の継続が困難になる事態も考えられます。
そこで、法定相続分とは異なる分割方法の指定として、後継者に指名したい者に対し、事業に必要な不動産や機械などの一切を承継させることを明記した遺言書を作成することで、事業承継をスムーズに行うことができるというメリットがあります。
以上に対し、特定の相続人に自分の財産を一切与えたくない場合もあります。この場合、相続人の廃除を行うことが考えられますが、相続人の廃除は遺言書に明記して行うことも可能です。ただし、相続人の廃除を実現させるためには、家庭裁判所の審判が必要であり、家庭裁判所が廃除を認めないこともある点に注意を要します。
【遺言書が必要な場合】
①特定の人に財産を多く与える
誰に対し、どの財産(どのくらいの割合の財産)を与えたいのか明記する
②相続人以外の人に財産を与える
・相続人以外の人(内縁の配偶者、お世話になった人等)に財産を与えることを示す
・相続人以外の人にどの程度の財産を渡したいのか明記する
③個人事業の後継者を指名する
法定相続分とは異なる遺産分割の指定として、後継者に指名した者に対し、事業に必要な一切の不動産や機械などを承継させると明記する
④相続人の廃除を行う
特定の相続人に財産を一切与えないことを示す(家庭裁判所の審判が必要)
【遺言書にはどんなことを記載するのか?】
遺言書にはどんなことを記載するのか
法的な効力が備わった遺言書を作成するためには、法律上意味のある事柄を記載することが必要です。これを「遺言事項」と呼ぶことがあります。
法律上意味のある記載事項は、①法律によって遺言でしか行うことが許される事柄に関する事項と、②遺言者の生前に他の方法で行うことができる法律上の事柄を、遺言によって行う場合に記載する事項、の2つに分類することができます。
まず、法律によって遺言でしか行うことが許されない事柄に関する事項として、遺贈を挙げることができます。
遺産分割方法の指定をする場合も、必ず遺言によらなければなりません。遺言執行者(遺言書の内容を実現してくれる人のこと)の指定も、遺言書を作成して明記することが必要です。
これに対し、他の方法でも可能な法律上の事柄に関する遺言の記載事項として、婚外子について父親が認知を行う際に、遺言で認知を行うことがあります。特定の相続人に自分の財産を与えたくない場合は、その特定の相続人を廃除する内容の遺言書を作成すれば、遺言者の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に審判の申し立てを行います。
【遺言書の種類】
遺言書は、どんな種類があるのか遺言書は、遺言者が、生前に、自分の死後の財産処分に関する意向を明確にすると共に、その意向に法的な効力を備えさせることができる重要な書面です。そのため、民法の定めによって、遺言書の作成について厳格な方式を求めています。
そして、民法が要求する遺言書の方式には、大きく普通方式と特別方式に分類することができます。【普通方式】には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
これに対して【特別方式】には、死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言の4つの方式があります。
このうち特別方式に含まれる4つの方式は、遺言者本人が書面を作成する余裕のない状況などを想定して、そのような状況に置かれた場合にも遺言をすることを保障するためのものです。特別方式による遺言ができる状況は非常に稀なので、私たちが遺言をするときは、普通方式によらねばならないと言えるでしょう。
普通方式に含まれる3つの方式は、いずれも「遺言書」という書面を作成することが必要とされています。遺言は遺言者の生前の意向を明確にすることを目的として作成するものですが、それは遺言者の死後に再確認することができないからです。
したがって、普通方式については、遺言書の作成について厳格な方式を要求するとともに、書面化を義務づけることによって、遺言者の意向が正確に反映されたものであることを、遺言者自身によって明らかにさせようとしています。
【普通方式とは】
①自筆証書遺言
【自筆証書遺言】はと、遺言者が書面に全文・日付・氏名を自書(自分で書くこと)した上で、その書面に遺言者が押印することによって、成立する遺言を言います。他人が遺言書の作成に関与しないので、誰にも知られることなく比較的簡単に作成することができます。
尚、2018年の相続法改正により、2019年1月以降は、添付書類である【財産目録】(持っている財産を一覧にした表のこと)に限り、自書による必要はなく、すべてのページに遺言者が署名押印をすることを条件として、パソコンなどで作成することが可能になりました。
②公正証書遺言
【公正証書遺言】とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、その内容を公証人が公正証書の形で書面化したものに、遺言者・証人・公証人が署名押印することによって、成立する遺言を言います。
公正証書遺言の作成は、遺言者が公証人や証人の目の前で、遺言内容を伝える手続きが必要ですので、他人が遺言内容を改ざんする危険が非常に少ないというメリットがあります。
しかし、公証人や証人の目の前で、遺言内容を知らせなければなりません。遺言者が誰にも知られることなく遺言を作成したい場合は、不向きな方式だと言えます。
③秘密証書遺言
【秘密証書遺言】とは、遺言者が遺言書を作成して封印し、その封書に遺言者・公証人・証人が署名押印して成立する遺言を言います。遺言の存在自体は明らかになりますが、本文を自書する必要がなく、遺言内容が他人に知られないというメリットがあります。ただし、秘密証書遺言については、自筆証書遺言よりも作成の手続きが煩雑であることから、あまり利用されていません。
【特別方式とは】
特別方式は例外的な方式である特別方式は、普通方式による遺言ができない状況の下で、例外的に認められる方式です。そのため、特別方式による遺言をした人が、普通方式による遺言ができる状態になった時点から6カ月間生存している場合、特別方式による遺言の効力が失われてしまいます。
①死亡の危急に迫った者の遺言
病気などのために死が差し迫っている人が、3人以上の証人の立ち合いの下で、そのうちの1名が遺言者から伝え聞いた(口授という)遺言内容を書面に起こすことによって、成立する遺言を言います。
遺言者が遺言をした日から20日以内に、家庭裁判所の確認を得なければ、遺言としての効力が認められません。
②伝染病隔離者の遺言
伝染病などのために隔離された人が、警察官1名と証人1名以上の立ち合いの下で、自ら遺言書を作成することによって成立する遺言を言います。遺言書を作成する際に自書であるか否かは問われません。
③在船者の遺言
船舶の上にいる人が、船長あるいは事務員1名と証人2名以上の立ち合いの下で、自ら遺言書を作成することによって成立する遺言を言います。伝染病隔離者の遺言と同様で、自書による必要はありません。
④船舶遭難者の遺言
船舶の上にいる人について、船舶が遭難したために死が差し迫っている場合に用いることができる遺言を言います。証人2名以上が立ち会いの下で、遺言者が遺言内容を伝え、証人が遺言内容を書面に起こすことになります。
証人は遺言者の目の前で書面を作成する必要はなく、証人もまた船舶が遭難している状況にあるため、遭難状態が解消された後に、書面を作成することも認められます。ただし、遺言者が遺言書の作成過程に関わっていないため、家庭裁判所の確認を得ることが必要です
【遺言書の代筆は認められるのか?】
遺言の方式によっては、公正証書遺言や秘密証書遺言など、遺言者が自書しなくても、遺言として有効と認められる場合もあります。
しかし、特に自筆証書遺言の場合は、遺言者自身が自書して遺言書を作成しなければ、遺言が無効になってしまいます。そこで、自筆証書遺言を作成する際に、代筆は許されないのか、どの程度まで他人が関与すると代筆と判断されるのかが問題になります。
自筆証書遺言は、遺言者の意向が正確に示されていることを、遺言者の筆跡によって作成された遺言書により明らかにする方式ですので、代筆は一切、許されません。ただし、病気等の影響で自力では字を書くことが困難な人について、遺言者の自由な筆記に対して影響を与える恐れがない形態での「添え手」の程度であれば、代筆にあたらず許されると考えられています。
【遺言の内容は法律で定められている】
遺言は、遺言者が生きている間に、自分の死後の財産処分に関する意向を明確にするための手段です。そして、遺言者が一方的に遺言書を作成することで、他人の置かれている地位が変動する等、法的な効力を発生させるのが遺言であると考えられています。
たとえば、遺言による未成年の婚外子(非嫡出子)の認知は、認知を受ける相手方(未成年の婚外子の側)の意向に関係なく、遺言者である父親と相手方との間に、いわば、強制的に親子関係を発生させる効力があります。これにより未成年の婚外子は、死亡した父親の財産を相続する権利を取得することができます。
このように、遺言は他人の置かれている地位を強制的に変動させるおそれがあるため、遺言をした内容について無制限に法的な効力を認めるわけにはいきません。
そこで、民法の定めによって、相手方が利益を得たり不利益を被ったりするなど、法的な効力が付与される遺言の内容を、ある程度限定しています。そして、一般的に法的な効力が付与される遺言の内容をのことを【遺言事項】と呼んでいます。
遺言事項については、法律によって遺言でのみすることが許される事柄に関する事項と、遺言者の生前に他の方法で行うことができる事柄を遺言でする事項の2つに大きく分類されます。
その他には以下のように、①相続、②相続以外の財産処分、③身分関係、④遺言の執行といった事柄に応じて、遺言事項を分類することもできます。
①相続に関する事柄
民法で定められている相続に関する事柄を修正(変更)する事項が挙げられます。主な事項は以下の通りです。
・相続人の廃除あるいは廃除の取り消し
・相続分の指定(指定相続分)あるいはその委託
・遺産分割方法の指定(相続させる旨の遺言)あるいはその委託
・特別受益者の相続分(持ち戻し免除の意思表示)
②相続以外の財産処分に関する事柄
遺言者が自分の死亡した時の財産処分について、相続以外の方法を望む場合があります。この場合、遺言者の中で明確にその考えを示しておく必要があります。主な事項は以下の通りです。
・遺贈(遺贈は相続人以外の人に対してすることも可能です)
・遺産に基づく一般財団法人の設立
・遺産に関する信託の設定
③身分関係についての事柄
親子関係といった身分関係についての事柄は、相続や財産処分に関する事柄以上に、遺言者の意思を尊重することが求められます。以下のような事柄は、遺言書の中で、明確に示しておく必要があります。
・婚外子(非嫡出子)に対する父親の認知
・子が未成年の場合の未成年後見人や未成年後見監督人の指定
④遺言の執行に関する事柄
遺言内容の実現に向けた事柄として、以下のような事柄を遺言しておくことが認められています。
・遺言執行者の指定あるいはその委託
・遺言執行者の報酬や複数名の場合の任務執行等
法律上の形式に反する遺言の効力
遺言には普通方式と特別方式があります。遺言者は自身が行おうとする遺言の種類に応じた方式に従うことで、遺言者が死亡した時に、その遺言の効力が発生します。
しかし、遺言の種類に応じた方式に違反して作成された遺言については、遺言としての成立が否定され、当然に無効と扱われます。例えば、自筆証書遺言において、パソコンを使って全文を作成した場合には、自筆証書遺言としての成立が否定されて無効と扱われます。
本人以外の者が遺言書を変更するとどうなる
遺言書の内容の一部について、追加・削除・訂正といった変更が必要になった場合には、遺言者本人が、変更する場所を指し示し、その場所について変更したことを自書した上で署名し、変更した場所に押印(遺言書に押印したものと同じ印鑑を使用します)することで、遺言書の変更を行うことができます。
遺言書の変更が必要になったら、以上の方式に従えばよく、全文を書き直すことが必要になるわけではありません。もっとも、遺言書の変更について遺言者の署名押印が求められているのは、遺言者自身による変更であることを明確にする目的があります。変更の権限を持たない他人による遺言書の内容の変更(改ざん)は許されません。
遺言者でない他人が遺言書の内容を変更した場合は、遺言書の変更の方式に違反したことになります。しかし、他人が変更したことによって、当然に遺言全体が無効になるわけではありません。
原則として、他人が変更をした部分のみが無効になり、変更がなされていない遺言として、依然として効力が認められます。
しかし、他人による変更によって、遺言自体の方式に違反する状態になったときや、元の文字を読むことが困難になったときなどは、遺言全体が無効になることもあると考えられています。
署名押印についての問題
遺言書に署名が求められているのは、遺言者を特定するという目的があります。したがって、遺言者が特定される限り、厳格に戸籍上の氏名を記載しなければならないわけではなく、通称を用いて記載することも許されます。一方、署名をしていたとしても、遺言者と第三者とを混同されるような記載がなされているときは、有効な署名として認めることができません。
遺言書に押印が求められているのも、遺言者の特定という目的からです。署名の他にも押印も要求することで、遺言者に再認識してもらう目的もあります。
押印の際には使用すべき印章については、とくに法律上の制限はありません。必ずしも実印によらなければならないわけではなく、認印や指印による押印も法律上は認められますが、できる限り実印を使用したほうが良いでしょう。特に公正証書遺言に遺言者が押印する印鑑については、実印を使用することを要求されるのが一般的です。
【遺言書の注意点】
問題となるのが、遺言書の文字が判読できなかったり、記載内容が一見すると矛盾するなどの理由で、遺言書に記載された内容が不明確な場合です。とくに自筆証書遺言においてトラブルの原因になることが多いようです。
まず、記載内容が不明確である理由が、遺言書が汚れて文字の判読が難しくなっていたり、推敲不十分で記載内容が矛盾しているように見えたりするなど、遺言者が意図したものでない場合には、遺言書が書き記した真意をくみ取って、遺言内容を解釈することが許されます。
その際には、遺言書作成当時の事情や、遺言者の置かれていた状況なども考慮することができます。しかし、解釈によっても遺言者の真意がくみ取られなければ、記載内容が不明確な部分は存在しないものとして扱うことになります。
日付の記載がない遺言書の取扱い
自筆証書遺言の場合、遺言者が自ら日付を自書することが必要とされており、日付の自書がない自筆証書遺言は無効です。
ただし、具体的に「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日」などの暦日を用いて記載しなくてもかまいません。遺言書が作成された年月日を特定できれば良いため、例えば「〇〇歳の遺言者の誕生日」と記載していれば、客観的に特定可能な日付が記載されたものとして認められます。
記載されている日付に誤りがあれば、遺言書の作成年月日が特定できないため、自筆証書遺言は無効になるともいえます。しかし、客観的に誤記があることが明らかな場合は、遺言者が本来記載しようとした日付に作成された遺言であると扱う余地があります。
遺言書が2通ある
遺言者は自由に遺言の取消し(撤回)をすることができます。たとえば、「先の遺言を取り消す」ことを明らかにした上で、新たに作成した「後の遺言」によって、先の遺言を取り消すことができます。
しかし、後の遺言で「先の遺言を取り消す」ことを明らかにしなくても、後の遺言の内容が先の遺言の内容と矛盾する場合には、後の遺言が有効であり、先の遺言は取り消されたものと扱います。
どんな場合に遺言の取消が問題になるか
遺言は、遺言者が生前に作成し、遺言者が死亡した時点で効力が発生します。しかし、生きている間に、遺言者が作成当初とは異なる考えを持つようになって、遺言の内容を変更したいと思う場合があるかもしれません。また、遺言者を取り巻く事情が変動し、遺言の内容を修正しなければならない場合もあります。
そこで、遺言の効力を生じる前であれば、遺言の取消し(撤回)が自由に認められています。遺言の全部を取り消しても良いですし、その一部の取消も可能です。
遺言の取消は遺言で行わなければなりません。遺言は作成時点における遺言者の考えを反映している点から、それを取り消す場合にも、遺言者の確かな考えに基づく取消であることを、遺言によって明らかにする必要があるためです。もっとも遺言を取り消すことが明確にされていなくても、前後の遺言の内容が客観的に両立不可能である場合は、前の遺言が取り消されたものと扱われます。
遺言の取消については、当初の遺言と同じ方式で取消を行うことは要求されていません。たとえば、当初の遺言が公正証書遺言の方式によって作成されていた場合、この遺言の取消を行うために作成した遺言が自筆証書遺言の方式であったとしても、民法が定める方式に従って作成されていれば、自筆証書遺言による公正証書遺言の取消が認められます。
尚、遺言の取消をしていなくても、遺言者が遺言書を意図的に破棄したときは、破棄された部分あるいは遺言全体が取り消されたものとして扱います。
遺産分割後に遺言書が発見されたときはどうなるか
遺産分割を終えた後に、故人(被相続人)が作成した遺言書が発見された場合は、遺産分割の効力が問題になります。遺産分割後に遺言書が発見された際に、とくに問題になるのは、遺産分割の当事者の範囲に影響が生じる場合と、遺産分割の対象である相続対象(遺産)の範囲に変動が生じる場合です。
当事者の範囲に変動が生じる場合として、遺産分割協議に参加していた相続人が遺言により廃除されていた場合が挙げられます。この場合、家庭裁判所で廃除の審判が確定すると、相続人でない人が参加したとして遺産分割の効力が否定され、再分割の必要が生じます。
これに対し、相続財産の範囲に変動が生じる場合として、遺言により遺贈(特定遺贈)がなされており、相続財産に含めることができない特定の財産を、遺産分割により相続人に分配してしまった場合が挙げられます。この場合、遺産分割全体に影響があるときは、遺産分割全体の効力が否定され、再分割の必要が生じると考えられています。
【公正証書遺言の作成方法】
公正証書遺言とは 、遺言者が伝えた内容を、公証人が公正証書の形式によって書面化する方式の遺言を言います。公正証書遺言の作成に関与する【公証人】は、公証役場に配置される公務員で、裁判官や検察官の経験者などから法務大臣が任命します。
そして、公証人が作成する公正証書は、個人の権利義務などに関する信用力の高い公文書であるため、公正証書の形式で作成される公正証書遺言は、後から遺言の効力をめぐる紛争が生じにくいという特徴を持ちます。
作成された公正証書遺言は、公証役場で保管されますので、第三者が遺言内容に改変を加える恐れはほとんどありません。さらに、自筆証書遺言とは異なり、公証人が遺言書を作成するため、遺言書の全文を自書することが困難な人であっても、公正証書遺言であれば作成できるという大きなメリットがあります。
どのように作成するのか公正証書遺言を作成する手順は、まず2名以上の証人が立ち会いの下で、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えます。これを口授といいます。
次に公証人は口頭で伝え聞いた内容について、筆記により書面を起こし、遺言者と証人に対し、筆記した内容の読み聞かせや閲覧を行います。そして、内容に不備がないことを確認した遺言者と証人が、書面に署名押印を行います。
最後に、公証人が正しい方式に従って、公正証書遺言を作成したことを添え書きした上で、公証人が署名押印することによって、公正証書遺言が成立します。作成された公正証書の原本は公証役場に保管されます。
その他に、原本とまったく同じ内容の書面として公証人が作成した謄本と、原本と同様の効力を持つ正本(遺言者や証人の署名押印が省略されています)が遺言者や遺言執行者に交付されます。つまり、公正証書遺言は合計3通作成されます。
【公正証書遺言作成のための必要書類】
公正証書遺言の作成を公証人に依頼するにあたり、事前に遺言者が用意しておくべきいくつかの必要書類があります。
・遺言者や相続人に関する必要書類
遺言者が自らの考えに基づき、公正証書遺言を作成することを確認するために、市区町村役場において遺言者の印鑑証明書(印鑑登録証明書)を発行してもらう必要があります。
相続人に自分の相続財産を遺すという内容の遺言にする場合は、その相続人に関する戸籍謄本が必要です。これは、相続人の続柄を確認するための資料ですので、相続人が自分の配偶者や子であれば、市区町村役場において遺言者の戸籍謄本を取得するだけで足ります。
しかし、代襲相続によって遺言者のおい・めい(遺言者の兄弟姉妹の子)が相続人になることもあります。この場合、遺言者の戸籍謄本からおい・めいの続柄を確認できませんので、これを確認するために遺言者の戸籍謄本とは別途、おい・めいの戸籍謄本が必要です。
これに対し、相続人以外の人に自分の相続財産を遺すという内容の遺言にする場合は、その人の住民票の写しなど、氏名、住所、生年月日が明らかになる書類が必要です。
尚、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票の写しは、発行日から3カ月以内のものでなければ使用できませんので、有効期限に注意しなければなりません。
・相続財産に関する必要書類
特に相続財産が不動産の場合は、不動産の所在や地番を特定する必要があるため、法務局において、不動産の登記事項証明書の取得が必要です。
その他、不動産の価値を把握するために、市区町村役場などに固定資産評価証明書などの発行を受けることも必要です。
・証人や遺言執行者に関する必要書類
公正証書遺言は2名以上の証人の立ち合いが必要です。未成年者、推定相続人(被相続人の死亡時に相続人になる人のこと)、受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者もしくは直系血族などは、証人になる資格がありません。
そこで、証人になる人の氏名、住所、生年月日、職業などが分かる資料を提出します。遺言執行者として相続人や受遺者以外の人を指定する場合は、遺言執行者になる人の氏名、住所、生年月日、職業に関する資料を提出します。
口授に関して公正証書遺言を作成する場合、本来であれば前述した手順に従うことが必要です。しかし、実際には口授に先立って、遺言者が公証人に対し、遺言の大体の内容を記したメモ書きなどを手渡し、それに基づいて公証人が事前に公正証書遺言を作成し、当日は遺言内容と一致しているのかを確認する意味で口授を受ける、という手順を踏んでいるケースが少なくありません。
この点については、全体として公正証書の作成手順が守られていると判断できれば、手順が入れ替わる形で作成された公正証書遺言も有効だと考えられています。
尚、口がきけない人については、公正証書遺言の最初の手順である「公証人への口授」が困難だと言えます。しかし、手話などによる通訳や本人の自書によって、公証人に遺言の内容を伝えることができれば、口授の代替手段として認めることができます。
【公正証書遺言を作成する際の手数料】
公正証書遺言を作成する際の手数料公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成するため、公証役場において手数料の納付が必要です。
手数料は相続財産の金額(評価額)に応じて異なりますが、相続財産が複数の場合は、それぞれの相続財産の金額に応じた手数料を合算します。
注意しなければならないのは、相続財産の合計額が1億円以下の場合は、手数料の合計額に1万1000円の加算が必要になるという点です(遺言加算といいます)
●公正証書遺言を作成する際の手数料●
相続財産の価額(手数料)
100万円以下(5,000円)
100万円を超え200万円以下(7,000円)
200万円を超え500万円以下(11,000円)
500万円を超え1000万円以下(17,000円)
1000万円を超え3000万円以下(23,000円)
3000万円を超え5000万円以下(29,000円)
5000万円を超え1億円以下(43,000円)
1億円を超え3億円以下(43,000円に5,000万円ごと13,000円加算)
3億円を超え10億円以下(95,000円に5,000万円ごと11,000円加算)
10億円を超える場合(249,000円に5,000万円ごと8,000円加算
【自筆証書遺言とは】
自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言書を手書きで作成することによって成立する遺言をいいます。
遺言者は、遺言の本文・日付・氏名を自書した上で、押印を行う必要があります。
自筆証書遺言は、文字を手書きで作成することによって成立する遺言をいいます。
遺言者は、遺言の本文・日付・氏名を自書した上で、押印を行う必要があります。
自筆証書遺言は文字を書くことができれば、基本的に誰でも利用することができる簡易な方式です。
公正証書遺言とは異なり、遺言書の作成に際して特別な費用を必要としないので、コストをかけずに遺言を作成したいと考える遺言者にとって、自筆証書遺言は経済的負担が非常に少ない遺言方式であるということができます。
ただし、自筆証書遺言にはデメリットもあります。まず、自筆証書遺言は簡易な方式であって、多くの人が選択する方式である反面、厳格な方式を良く理解せずに作成したため、遺言書全体が無効になってしまうことが少なからずあります。
また、公正証書遺言とは異なり、遺言の作成にあたって公証人や証人などの他人が立ち会うことなく作成可能ですので、自分の死後まで遺言内容を他人に知られたくないと考える遺言者にとって、自筆証書遺言は理想的な方式だと言えます。
しかし、内容を秘密にできる反面、相続人が遺言書の存在を知らないまま、相続人同士の遺産分割協議によって遺産が分配されてしまう恐れがあるなど、遺言者の意向が軽視される危険があります。
【自筆証書遺言の保管制度】
かつては、自筆証書遺言を適切に保管する法制度が存在していませんでしたので、例えば、遺言者の死亡後に相続人になることが予定されている人(推定相続人)が自筆証書遺言をひそかに発見し、内容を自己に都合が良いように書き換えたり(変造)、場合によっては自筆証書遺言自体を破棄してしまうことがありました。
そこで、2018年相続法改正により、2020年7月までに【自筆証書遺言の保管制度】を導入することになりました。しかし、これにより自筆証書遺言の保管が義務づけられるわけではありませんので、他人による変造や破棄などから遺言書を守るためには、やや手続きが煩わしいものの、公正証書遺言の方式を用いることが最適だと言えるでしょう。
遺言者本人による遺言書の自書が必要である自筆証書遺言の要件として、公証人や証人の立ち合いは求められていません。自筆証書遺言の要件として民法が定めているのは、遺言の全文・日付・氏名を遺言者が「自書」する(手書きする)ことと、作成した遺言書に押印することです。
したがって、自筆証書遺言が有効か無効かを判断するときは、遺言者本人が遺言書を自書したか否かがポイントになります。
自筆証書遺言において自書を要求しているのは、筆跡から遺言者自身が記載したことが判明すれば、その遺言書は遺言者自身の考えに基づいて作成されたことを確認できるからです。
したがって、遺言者が伝えた内容を第三者が聞き取った上で文書を作成したような場合(他人が代筆をした場合)や、遺言者自身がパソコンなどを利用して遺言書を作成したような場合(手書き以外の方法で作成した場合)は、遺言者本人が遺言書を自書していないため、自筆証書遺言書としては無効になります。
同様に、文書を作成せず、動画を録画するなどの方法で、遺言者自身が音声などのメッセージで遺言を行うことも、遺言者の筆跡との照合ができないため、自筆証書遺言書としては認められません。その一方で、遺言者の筆跡との照合が可能であればよいため、複写の方法で作成された遺言書は、自書したものと認められます。
相続法改正で自書の要件が緩和された 自筆証書遺言の場合は、遺言者の生前の意向を確認する手段として、全文を「自書」することが要件として定められています。しかし、全文を自書することは、特に高齢の遺言者にとって容易でないことがあります。
徐々に死期が迫ってきている状態で、全文を判読しやすい文字で書くのを要求することも、遺言者に対して大きな負担になっています。そのため、かつてから自筆証書遺言を利用することのハードルが高すぎることが批判されていました。
そこで、2018年の相続法改正により、全文の自書の要件が少し緩和されました。(2019年1月13日より施行)。具体的には、自筆証書遺言の全文について、遺産の詳細を明らかにする添付書類としての【財産目録】に関する事項に限って、自書以外で作成しても良いことになりました。
この改正により、パソコンなどを用いて財産目録を作成することができます。また、財産目録は遺言者自身が作成しなくても良いため、他人に代筆を依頼することができます。
それ以外にも、遺産が不動産の場合は、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーを添付し、遺産が預金の場合は、通帳のコピーを添付することができます。
全文自書の要件の緩和は、自筆証書遺言を作成する上で、大きな労力を割かなければならなかった財産目録の作成について、自書以外の方式が認められ、これまでよりも比較的容易に自筆証書遺言の利用が可能になります。
ただし、財産目録以外の全文や、日付・氏名については、依然として自書が必要であることに注意を要します。
一方、自書以外を可能にしたことで、財産目録を他人が書き換える(改ざんする)などの危険性が高まります。そこで、自書以外の方法で作成した財産目録については、すべてのページに遺言者が署名押印することを要求します。財産目録が両面に渡るときは、表面と裏面の双方に署名押印が必要です。
自筆証書遺言の保管制度の創設2018年の相続法改正に伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、この法律に基づいて自筆証書遺言の保管制度が創設されました。(2020年7月1日に施行)
遺言者は自筆証書遺言の保管を遺言書保管所(法務局)に依頼することができます。保管された遺言書は、画像データ化され、遺言者の死後に、相続人や遺言執行者などの請求があれば、その画像データのほうが交付されます。
【遺言書は勝手に開封してはいけない】
遺言書は勝手に開封してはいけない
自宅などで「遺言書」と書かれている封筒を発見した場合、勝手に開封してはいけません。必ず、家庭裁判所に封筒を提出し、相続人などの立会いの下で開封しなければなりません。この手続きを遺言書の【検認】と言います。
遺言書の検認は、相続人などの立会いの下で、家庭裁判所が遺言書を開封し、遺言書の存在と内容を認定する手続きです。
遺言書の検認によって、検認時の遺言書の存在と内容を確定してもらえるため、検認後の遺言書の改ざんを防止できます。
遺言書の検認が必要になるのは、公正証書遺言以外の方式で作成された遺言書です。ただし、自筆証書遺言については自筆証書遺言の保管制度によって保管されていれば、遺言書の検認が不要です。
封筒に入っている遺言書だけではなく、封筒に入っていない遺言書も、改ざんを防止する為に遺言書の検認が必要とされています。
遺言書の検認では、遺言書が民法の定めている方式に従って作成されているかどうかが調査されます。しかし、遺言書の内容が遺言者の意向に基づいているかどうかまでは調査されません。
遺言書の検認を受けずに遺言書を開封した場合、ただちに遺言が無効になるわけではありませんが、遺言書の改ざんなどが争われるリスクが非常に高まります。
また、検認を受けずに開封した場合は5万円以下の過料に処せられます。
家庭裁判所における遺言書の検認の手続き
遺言書の検認を受ける手続きは、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人が被相続人(遺言書の作成者)の最後の所在地を管轄する家庭裁判所に対し、検認の申立てを行います。
検認の申立てに必要な書類は、①遺言書(封筒に入っていない遺言書はそのままの状態で提出します)、②申立書(裁判所のホームページからダウンロード可)、③被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、④相続人全員の戸籍謄本などです。
これらの必要書類を準備した上で、遺言書1通につき800円の収入印紙と連絡用の郵便切手を添えて提出します。
検認の申立てが受理されると、裁判所から相続人に対して検認期日が通知されます。検認期日には、申立人が遺言書などを持参して家庭裁判所へ出頭し、同じく出頭した相続人などの立会いの下、家庭裁判所が遺言書を開封し、その内容を確認します。
なお、申立人以外の相続人などが検認期日に出頭するかどうかは自由とされています。
検認の手続きが終了した後は、家庭裁判所に対し検認済証明書の交付申請を行います。相続登記や預金口座の名義変更などの相続手続きをする場合は、検認済証明書の提出が必要になりますので、必ず交付申請をするようにしましょう。
【遺言執行者とは】
【遺言執行者】とは、遺言者の遺言内容が公正に実現されるように、遺言の執行に関する事項を担当する人を指します。
被相続人が遺言を遺した場合、相続人は、被相続人の一切の権利義務を承継する(包括承継)という立場から、遺言の内容を実現するために一定の義務を負うことがあります。
たとえば、遺言によって第三者に対する遺贈が行われた場合、相続人は遺贈義務者として、遺贈を受けた人(受遺者という)に対し、遺贈の対象である財産を引き渡す義務を負うことになっています。
その一方で、とくに相続人が複数人いる場合などは、相続人同士の利害関係が対立するため、公正な遺言内容の実現を望むことが難しい場合があります。そこで、遺言内容の公正な実現のために選任されるのが遺言執行者です。遺言執行者に就任する資格については、未成年者や破産者以外の人であれば、特段の制限はありません。ただ、遺言執行者は様々な手続きを実行することが必要ですから、弁護士などの専門家に就任してもらうケースが多いようです。
遺言執行者は、遺言者が遺言で選任するか、遺言者が遺言において委託した第三者が選任するのが原則です。しかし、遺言執行者に選任された人が就任する義務はなく、遺言執行者への就任を辞退することも可能です。
辞退により遺言執行者が不在になった場合は、相続人などの関係者からの請求に基づき、家庭裁判所が選任することができます。一方、遺言執行者が遺言内容の実現に向けた任務に反する行為などをした場合、相続人などの関係者は、家庭裁判所に対し、解任の請求をすることができます。
どんなことをするのか
遺言執行者は、遺言内容の実現に必要とされる一切の行為をする権限を持っており、相続人全員の代理人とみなされます。遺言執行者が選任されている場合、相続人は、遺言内容を執行する権限を失いますから、遺言を執行しても無効になることに注意を要します。
さらに、遺言によって婚外子(非嫡出子)の認知あるいは相続人の廃除とその取消しをする場合、婚外子の認知の場合は届出、相続人の廃除とその取消しの場合は家庭裁判所へ申し立てができるのは、民法の定めによって遺言執行者に限定されています。
その他、遺言執行者は就任した時点で、自らが管理すべき相続財産の状況を把握するため、財産目録を交付する必要があります。
このように、遺言内容の実現に向けて、遺言執行者には広い代理権が認められているため、遺言執行者の行為が、時として相続に関して権利を持つ人(被相続人に融資していた貸主など)に影響を与えることもあります。2018年相続法改正(2019年7月1日に施行)により、遺言執行者であっても、相続に関して権利を持つ人の権利行使を妨害してはならないとする定めが設けられています。
相続についてより詳しく学びたい方
この「相続読本」は相続なんでも相談センターが長年に渡って培った相続のノウハウが詰まった1冊です。何から始めていいかわからない方、何を調べて、何を勉強すればいいのかわからないでも必ずこの1冊の中に知りたいことが詰まっています。
是非一度、手に取ってみてください。こちらのページからダウンロードできます。