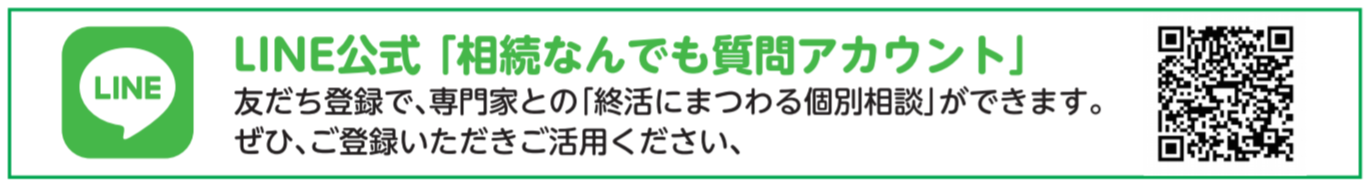認知症の基礎知識
2020/10/28
目次
【エンディングノートの完成をお手伝いします】
終活について、知っておくと困らないこと、家族を困らせないために必要なこと。そんな終活についてのヒントをお届けし、あなた独自のエンディングノートを完成をお手伝いします。
【認知症の 基礎知識 】
厚生労働省によると、日本の認知症高齢者の数は2012年時点で462万人と考えた場合、2025年の認知症の有病者数は約700万人となります。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000519620.pdf
2025年の65歳以上の人口は3677万人に達すると見込まれています。ということは、約5人に1人が認知症になると推計されます。
認知症は加齢にともなって発症しやすくなり、認知症高齢者の約8割が80歳以上という調査結果もあります。
【認知症の定義】
一口に認知症といっても、きちんと定義をしておかなければ、その症状を特定することができないので、定義を明確にしておきましょう。
認知症とは、何らかの病気によって脳のはたらきが低下し、日常生活や仕事に支障をきたした状態を指します。
自然な老化に伴う認知症では、脳のダメージの程度、症状、生活のしづらさが明らかに違います。
一般的に、認知症というと記憶障害(物忘れ)がクローズアップされますが、記憶は認知機能の一つにすぎず、その症状は多岐に渡ります。
たとえば、暴言や反社会的行為などを引き起こす症状もあります。
また、認知症は誰がなってもおかしくない、身近なことです。
【認知症の主な症状と対処法】
認知症の症状は多岐にわたりますが、大まかにいうと次のように分類できます。
●認知機能の障害によって引き起こされる「中核症状」
●中核症状をもとに、性格や環境などの要因が絡んで引き起こされる「周辺症状(BPSD)」主な中核症状としては、「記憶障害」「見当識障害」「失行」「失認」「実行機能障害」が挙げられます。
中核症状① 記憶障害
認知症の中核症状としてよく見られるのが、記憶障害です。
認知症を発症すると、早期に記憶する能力の障害が起きます。
健常な人でも年齢を重ねるほどに物忘れが多くなりますが、何かヒントや小さなきっかけがあれば思い出すことができます。
しかし、認知症の記憶障害では数分前に見聞きしたことや自分がした行動でも思い出せなくなってしまうのです。
症状が進行するにつれ、以前は覚えていたはずの記憶も欠損していきます。
まだ忘れずに残っている記憶を頼りにするため、自分の現状を把握できなくなることも。
アルツハイマー型認知症でとくに、経験したできごとに関する「エピソード記憶」が思い出せなくなることが多いです。
<症状例>
●財布を一時的に机の上に置いたのに、それを忘れてしまって、財布が身の周りから無くなって盗まれたと勘違いする。
●食事をしたことを忘れてしまって、食事を食べさせてもらえないと感じする。
●仕事を退職したのに、仕事着に着替えて出勤しようとする。
<対処法>
財布などの小物は常に身に着けてもらったり食事をする度に記録をつけたりするような工夫をしましょう。
そうすることで、高齢者はメモを見て自分の覚えたことや行動を見直すことができます。
中核症状② 見当識障害
今日が何月何日で、今何時くらいかが分からない。
自分がどこにいるのかが分からない。
知っているはずの人を見ても、どんな人だったか思い出せない。
周りの人間と自分との関係が分からない・・・。
このように、自分の置かれた状況が把握できなくなり、ひとり取り残されてしまったような状態になるのが見当識障害です。
とくに引っ越しや入院など、環境がかわったときに強く現れるようになります。
<症状例>
●自分の家ではないと思って、外に出て行こうとする。
●夏なのに暖房をつけたり、厚着をしたりする。
●夜中なのに朝だと思い、起きて新聞を取りに行く。
●家の中の場所が分からなくなり、トイレ・風呂場に行けない。
●近所に出かけたら、自分の家に戻ってこられない。
●毎日会っている家族は認識できても、家族ではない親戚や友人と自分の関係性が分からない。
<対処法>
見当識障害の方は自分が孤独だと感じやすいので、介護者が常に近くにいる状況をつくることが大切です。
また、外の環境に対する管理能力が乏しくなるので、服装を含めた体温調節や季節特有の対策をしてあげるようにしましょう。
徘徊や家に出ると戻れなくなるからといって屋外の刺激を断つと、逆に症状を進行させてしまいます。
自分の足で歩いたり、歩いたときの景色の変化、季節の変化を感じたりすることが脳には良い影響をもたらします。
中核症状③ 失行
体を動かせるにもかかわらず、目的をもった行動の方法が分からなくなる状態を「失行」といいます。
以前は普通にできていたことができなくなってしまいます。
<症状例>
●服をきちんと着ることができない・鍵穴に鍵ではない物を入れて開けようとする。
●じゃんけんができない。
●お箸を上手に使って食事をすることができない。
<対処法>
介護者は見守りながら、できない時だけ手を貸して教えてあげるようにしましょう。
すべてをやってしまうと余計に何もできなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
中核症状④ 失認
体の器官(目・耳・鼻・舌・皮膚等)に問題がないにも関わらず、視覚・聴覚・触覚・臭覚・味覚の五感に関係する認知能力が正常に働かなくなる状態を「失認」といいます。
五感のすべてに一気に障害が現われるのではなく、一部分から欠損していくことが一般的で、周囲の人が支援すれば正しく認識することができます。
<症状例>
●ゴミ箱をトイレと間違える。
●遠近感がなくなる。
●府振られていることはわかるが、部分が分からない。
<対処法>
こちらも介助者が、誘導してあげたり補佐役に努めるようにしましょう。
中核症状⑤ 失語
脳梗塞などの原因で血管性認知症になってしまい、脳の言語に関わる部位が損傷することで「聞く・話す・読む・書く」といった音声・文字などの言語情報の機能が失われた状態を「失語」といいます。
言語障害があると、自分と他人とのコミュニケーションがうまくできなくなり、抑うつ状態になりやすくなります。
<症状例>
●話せる言葉の数が少なくなり、言葉の長さも短くなる・サラサラとしゃべっていても、内容の意味がない・相手の話を意味ある文章だと理解できない(感覚性失語)・相手の話が聞こえて意味を理解できても、自分は話せない(運動性失語)
●読めても言語を理解できない。
●言葉は理解できても復唱できない。
●文字が書けない。
●計算ができない。
<対処法>
長い言葉や文章を使うのをできる限り避けること。簡単な言葉でゆっくりと話したり、ジェスチャーを使ったりすると理解しやすくなります。
また、1度で理解できないこともあるので、繰り返したり少し表現を変えて伝えるなどの工夫も必要です。
中核症状⑥ 実行機能障害
計画を立てて順序よく物事を行うことができなくなることを「実行機能障害」といいます。
ある目標に向かって手順通りにできない、自立できないことで日常生活をひとりで送れなくなってしまいます。
<症状例>
●食事の準備ができない。
●計画的な買い物ができない。
●電化製品の使い方が分からない。
●予定外の出来事に対処できない。
<対処法>
何かを一緒になってできるようにしていくこと。食事の準備も一緒に行ないながら細かく段取りや作業を確認したり、買い物をするときも前もって購入品を紙に書き、次はどこへ行って何を買うのかを確認しながら過ごしてみると良いでしょう。
【周辺症状(BPSD】
中核症状をもとに、性格や環境などの要因が絡んで起こるのが「周辺症状(BPSD)」です。
認知機能の低下につれ、不安感や焦燥感に襲われたり、幻覚に悩まされたりするようになります。
さらに「落ち着きなく徘徊する」「急に大声を上げる」といった、周囲から見て不可解な行動も。
特に問題になるのは、被害妄想にとらわれて「暴言を浴びせる」「暴力をふるう」といった攻撃的な言動が多くなる場合です。
最悪の場合、傷害事件や殺人事件などにも発展します。深刻な場合は、専門家に相談をすることも大切です。
認知症による迷惑行為や反社会的行為は、周囲から見ると、理不尽、不可解なものです。
してはいけないことを認知する機能が損なわれてしまうと、家族が叱ったり諭したりしても改善は見られなくなります。早めに専門家に相談した方が良いでしょう。
【認知症のタイプ】
認知症には様々なタイプがあり、それぞれ原因や症状が異なります。特に次のタイプが良く知られています。
●アルツハイマー型認知症(アルツハイマー病)認知症の中でも最も多く、全体の約6割を占めているタイプです。脳細胞が破壊され、脳が委縮することで起こります。主に記憶に関する障害がみられます。
●脳血管性認知症アルツハイマー型に次いで多く、全体の約2割がこのタイプです。脳の血管が詰まったり、破れたりすることで起こります。高血圧、動脈硬化、糖尿病等、血管に関係する病気が原因になります。
●レビー小体型認知症最近増えているタイプで、全体の約1割にあたります。レビー小体という物質が脳内に蓄積することで起こります。幻視や意識の混乱などの症状がみられます。●前頭側頭型認知症全体の数パーセントの割合で存在。脳の前頭葉、側頭葉に変異が生じることで起こります。衝動的、反社会的な行動が見られ、事件や犯罪につながりやすいタイプです。
認知症のタイプによって対策が異なる
アルツハイマー型認知症は、脳内にたんぱく質が蓄積され、それが脳細胞を破壊し、脳が委縮することで起こります。一方、脳血管性認知症は、脳血管の障害が原因です。一言で認知症といっても、このようにタイプが違えば対策も異なります。