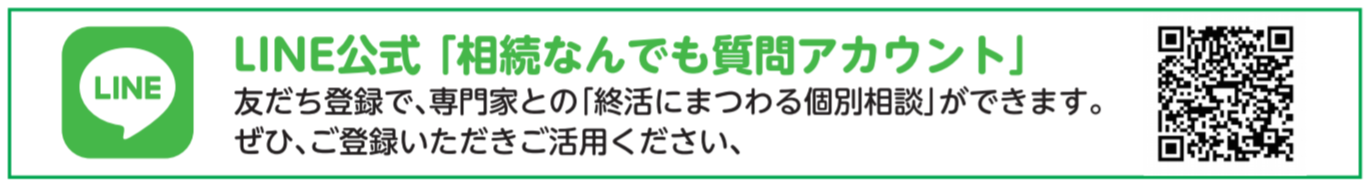認知症と終活
2020/10/28
目次
【エンディングノートの完成をお手伝いします】
終活について、知っておくと困らないこと、家族を困らせないために必要なこと。そんな終活についてのヒントをお届けし、あなた独自のエンディングノートを完成をお手伝いします。
【認知症で困ること】
認知症になると、もともと当たり前のようにできていたことができなくなってきます。自立した生活が困難になり、介護してくれる家族に大きな負担をかけるかもしれません。また、症状が進んだり、人間関係のこじれなど、老人ホームから退去を求められる可能性もあります。その中でも問題になりやすいのは、やはり、財産の管理の問題です。例えば、以下のようなトラブルが発生してしまうことがあります。
●預貯金や不動産など所有している財産を把握できない
●自分の生活に必要な金銭の管理ができない
●売買や賃貸借などの契約で正常な判断ができない
●詐欺などの被害にある危険性が高まる
安心してお金の管理を任せられる家族(配偶者や子など)がいるのであれば、それほど深刻な問題にならずに済みかもしれません。
しかし、家族の仲があまりよくなり、ムダ遣いをされるのが心配、あるいは頼れる家族がいないといった場合には、どうすれば良いか、このあたりが問題となります。
こうした場合には、後見人(成年後見人)と呼ばれる代理人を立てることが有力な選択肢の一つとなります。
【認知症と後見人、どのような制度なのか?】
認知症などに判断能力が十分ではなくなった人は、財産管理や契約などを正常な判断にもとづいて行うことが困難です。こうした人を法律的に支援する立場の人は、「成年後見制度」という制度があります。この制度により本人を支援する立場の人は、「成年後見人」と呼ばれます。(成年後見人は、本人の判断能力の度合により、「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかになります)
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
●任意後見制度本人が元気なときに、後見人になってもらいたい人と公証役場で契約書を作成しておくもの。判断能力が低下した際に、後見人になる人や親族などが家庭裁判所に申し立てることで利用できます。
●法定後見制度すでに判断能力が低下しているときに利用できるもの。家庭裁判所に申し立てをして、家族や親族または専門家を後見人等として選任してもらいます。
成年後見人は何を行う人なのか?
成年後見人の職務は法律行為の代理や同意・取り消しで、主に次の2つを行います。
●財産管理現金・預貯金・不動産・有価証券などの管理、税金、公共料金、保険料などの支払い
●身上監護福祉・介護・医療などに関する契約や手続きなどの代理や同意・取り消し。※契約や手続きの代理であり、生活や介護そのものの支援ではないことに注意してください。
【成年後見制度を利用する際の注意点】
●財産の移転が自由にできなくなる空き家の自宅を賃貸する、不要な不動産を売却する、預貯金を運用するなどのことはできません。不動産の売却代金が本人に必要な場合などは、家庭裁判所に申し立てをして承認を得る必要があります。
●後見人は原則として辞められないいったん後見人を引き受けると、原則として辞めることができません。身内が引き受ける場合、事前に職務範囲や報酬について理解や了承を得ておき、その上で引き受けることが重要です。
【認知症と相続】
認知症による判断能力の低下は、相続においても問題になります。家族(相続人)が認知症の場合、本人(被相続人)が認知症の場合が考えられます。それぞれ見てみましょう。
<本人(被相続人)が認知症の場合>
本人(被相続人)が認知症の場合に問題となりやすいのは、遺言書の効力に関する問題です。
例えば、次のような家族があったとします。被相続人・父、相続人・母、長男、次男。長男に自宅他、財産の多くを遺す旨の遺言がありました。
しかし、次男はこれを不服として、父が遺言を遺したときは、すでに認知症であったため、その遺言は無効であると主張することもあり得ます。
こうなると、非常に話がややこしくなります。遺言を遺したときの父の判断能力を証明する術がありません。医師に認知症とはっきりと認知症と診断を受けた前か後かといった問題もありますが、遺言の場合、法的には一概に「認知症=遺言能力がない」と判断されるわけではないのです。
このようなもめごとになると、泥沼の争いになるので、親族がバラバラになってしまう可能性があります。明らかに正常な判断能力のある時期に遺されたものであれば、問題はありません。
たとえ、後に認知症になったとしても有効性には問題はありません。判断能力があり、心身ともに元気なうちに遺言書を作成しておくことはとても大事なことといえるでしょう。
<家族(相続人)が認知症の場合>
家族(相続人)の中に認知症と診断された人がいると、相続人が亡くなった後の遺産分割協議を行うことができなくなります。
このような場合は、成年後見人が必要となります。仮に、身内が後見人を引き受けたとします。
すると、身内の場合は、遺産分割においては利益相反関係になってしまうのです。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要が出てきます。
例えば、先ほどの例の被相続人・父、相続人・母、長男、次男の場合で考えてみます。もしも、母が認知症で長男が後見人となっていた場合は、遺産分割協議を行うことができません。
母も長男も共に相続人であり、利益相反になるからです。このような場合は特別代理人として専門家に依頼することになります。
そうなると、専門家への報酬が発生することを考えておかなければなりません。
また、遺産を分けたように分けられない可能性もあります。
さらに後見人が身内の場合、後見人に後見監督人がつけられることもあり、専門家への報酬の支払いが長く続いていくことにもなりかねません。
判断能力があり、心身ともに元気なうちに遺言書を作成しておくことで、こうした問題を回避して、被相続人の意志によって遺産分割を行うことができます。
遺言書を作成することの大切さがわかります。