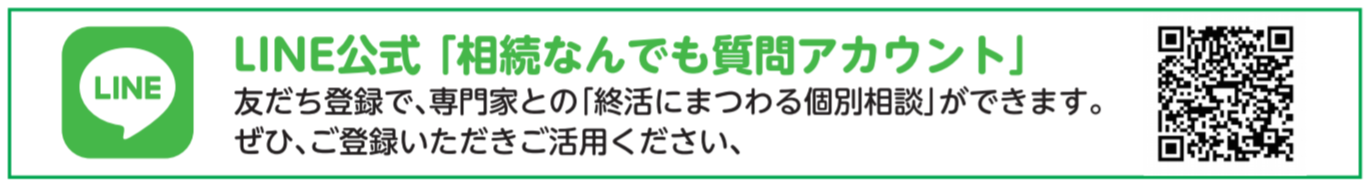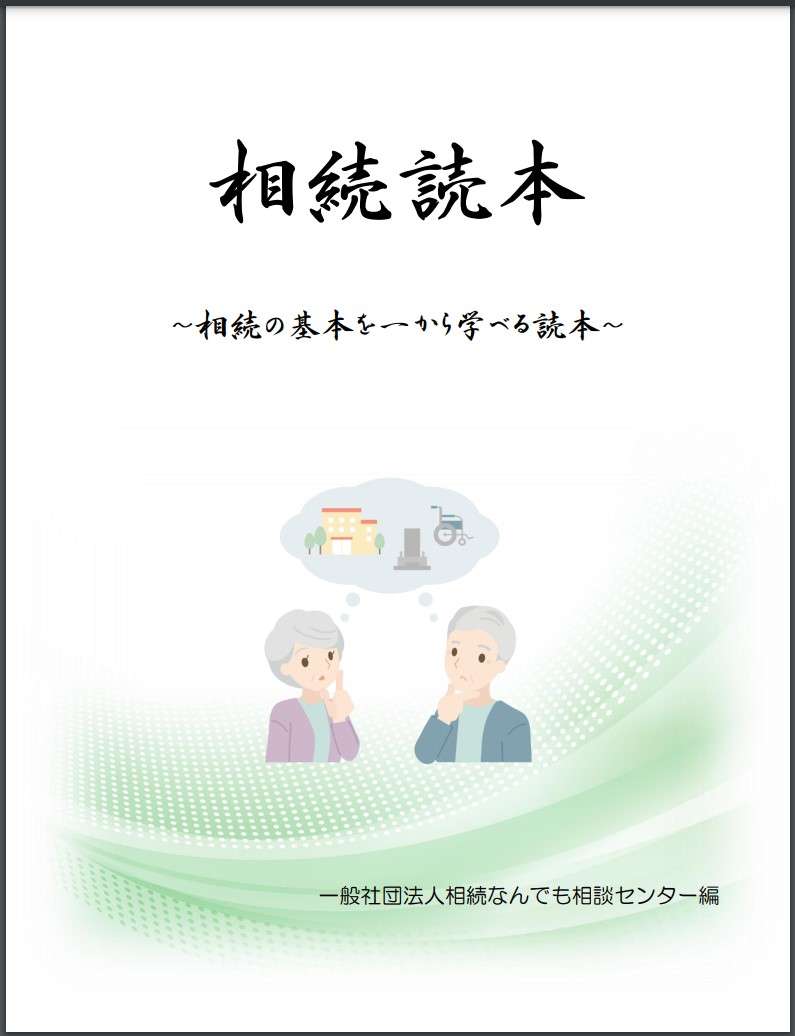遺贈
2021/01/22
目次
【遺贈は遺言で財産を一方的に与えることである】
「遺贈」とは、遺言によって、自分が指定した人(受遺者)に対し、自分の財産を一方的に与えることを言います。遺贈をする場合は、必ず遺言書を作成することが必要です。
その一方で、受遺者は相続人にする必要はなく、誰でもかまいません。後述するように、遺贈は財産を与える方法に応じて、特定の財産を与える特定遺贈と、割合で財産を与える包括遺贈に分類することができます。
もっとも、被相続人自らが死亡することで相続が始まるため、遺言書を作成しなくても、相続人に対しては自動的に自分の財産を自分の死後に与えた状態が作り出されます。後は相続人全員が遺産分割協議に参加し、話し合いなどで相続財産を分配すれば良いわけです。
しかし、自分が死んだ後は、自分の財産を相続人以外の人物や団体に与えたいと考える場合は遺言書を作成して遺贈をすることが求められます。たとえば、自分の死後は内縁の配偶者や慈善団体に自分の財産を与えたいときは、これらの者に遺贈をしておきます。
【遺贈は「遺言」によって行う】
遺贈は財産を一方的に与えるものなので、受遺者の意向とは無関係に、遺言者が死亡した時に効力が発生します。遺贈の内容を実現する者(遺贈義務者)は、原則として相続人ですが、遺言執行者がいる場合は遺言執行者です。遺言義務者は、受遺者に遺贈の対象になっている財産を譲り渡す義務を負います。その一方で、受遺者は遺贈を受け入れるかどうかを選択できます。遺贈の受け入れを認めることを遺贈の承認といい、受入れを拒否することを遺贈の放棄と言います。
そして、遺贈は「遺言」によって行うので、遺言が必要な方式に違反している場合などは、遺言が無効になる結果として、遺贈も無効になります。また、遺贈は相続と異なり、遺言者の死亡時に受遺者が死亡していた場合について、相続における代襲相続のような制度はありません。つまり、受遺者の相続人が代わりに遺贈を受けることは認められていません。
遺贈の目的物については、相続財産に含まれる範囲に限られており、遺言者の死亡時に遺贈の目的物が相続財産の範囲に含まれていなければ、原則として遺贈は無効になります。
【死因贈与と遺贈の違い】
遺贈と類似した行為として死因贈与があります。死因贈与とは、財産を与える側の人(贈与者)が死亡した時に、財産を受贈者に与えるという効果が発生する贈与契約(財産を無償で与える契約のこと)を言います。
死因贈与は、財産を与える側の人の死亡時に効力が発生する点で、遺贈と共通しています。しかし、死因贈与は「契約」であることから、遺贈のような厳格な方式に従う必要はありません。
これに対し、遺贈は、遺言という民法が定める厳格な方式を用いるため、これに従った遺言書の作成が必要です。たとえば、自筆証書遺言の方式を用いる際は、全文の自書と署名押印が必要です。
【相続させる旨の遺言と遺贈との違い】
遺言書で相続人に財産を与えるときは、遺贈ではなく「相続させる旨の遺言」を用いるのが一般的です。相続させる旨の遺言とは、被相続人が持っている特定の財産を相続人に相続させる遺言のことで、相続人だけに対して行うことができます。
例えば、遺言書に「〇〇市〇〇町にある建物を相続人Aに相続させる」と記載した場合に、相続させる趣旨の遺言として扱われます。単に「与える」と記載するのではなく、「相続させる」と記載するのがポイントです。
このような相続させる旨の遺言がある場合、「〇〇市〇〇町にある建物」の帰属先が「相続人A」になることが確定し、これに反する遺産分割ができなくなります(【遺産分割方法の指定】と言います)。その結果、相続人Aは単独で所有権移転登記の申請手続きができます。
これに対し、相続人が不動産の遺贈を受けた場合、所有権移転登記の申請手続きは、他の相続人との共同申請(遺言執行者がいるときは遺言執行者との共同申請)になります。他の相続人(あるいは遺言執行者)が協力してくれなければ、訴訟の提起が必要です。
【特定遺贈とは】
特定遺贈とは、特定の財産を遺贈することです。たとえば、遺言書に「〇〇市〇〇町にある土地Bを遺贈する」「現金100万円をBに遺贈する」と記載するのが特定遺贈の例として挙げられます。
特定遺贈における受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも特定遺贈の承認や放棄ができます。ただし、いったん特定遺贈の承認や放棄をすると、後から撤回はできなくなることに注意を要します。
また、受遺者が特定遺贈の承認も放棄もしない場合、相続財産の行方が確定しないという不安定な状態が生じます。そこで、遺贈義務者などは、受遺者に対して、期間を定めた上で、特定遺贈の承認や放棄をするように催促ができます。この催促に受遺者が応答しない場合は、特定遺贈を承認したものと扱います。
【包括遺贈とは】
包括遺贈とは、相続財産の全部あるいは「〇分の〇」という分数的割合で示した一部を遺贈することです。たとえば、遺言書に「相続財産の全部をCに遺贈する」「相続財産の3分の1をDに遺贈する」と記載するのが包括遺贈の例として挙げられます。包括遺贈の最大の特徴は、受遺者が相続人と同じ地位に立つことです。そのため、不動産や現金などの積極財産と共に、借金などの消極財産も取得します。
さらに、包括遺贈の承認や放棄も相続の承認や放棄と同様に行います。具体的には、包括遺贈を放棄する場合は、自分のために包括遺贈があったのを知った時から3カ月以内(熟慮期間内)に、家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述べをします。これに対し、包括遺贈の限定承認をする場合は、相続人全員や他の包括遺贈と共同して、熟慮期間内に限定承認の申述べをします。何もしないで、熟慮期間を経過すると、包括遺贈を単純承認したものと扱われることに注意が必要です。
●特定遺贈と包括遺贈のまとめ
<特定遺贈>(例)所在地を示した土地
<包括遺贈>(例)相続財産全部
本日はここまで。ありがとうございました。
相続についてより詳しく学びたい方
この「相続読本」は相続なんでも相談センターが長年に渡って培った相続のノウハウが詰まった1冊です。何から始めていいかわからない方、何を調べて、何を勉強すればいいのかわからないでも必ずこの1冊の中に知りたいことが詰まっています。
是非一度、手に取ってみてください。こちらのページからダウンロードできます。