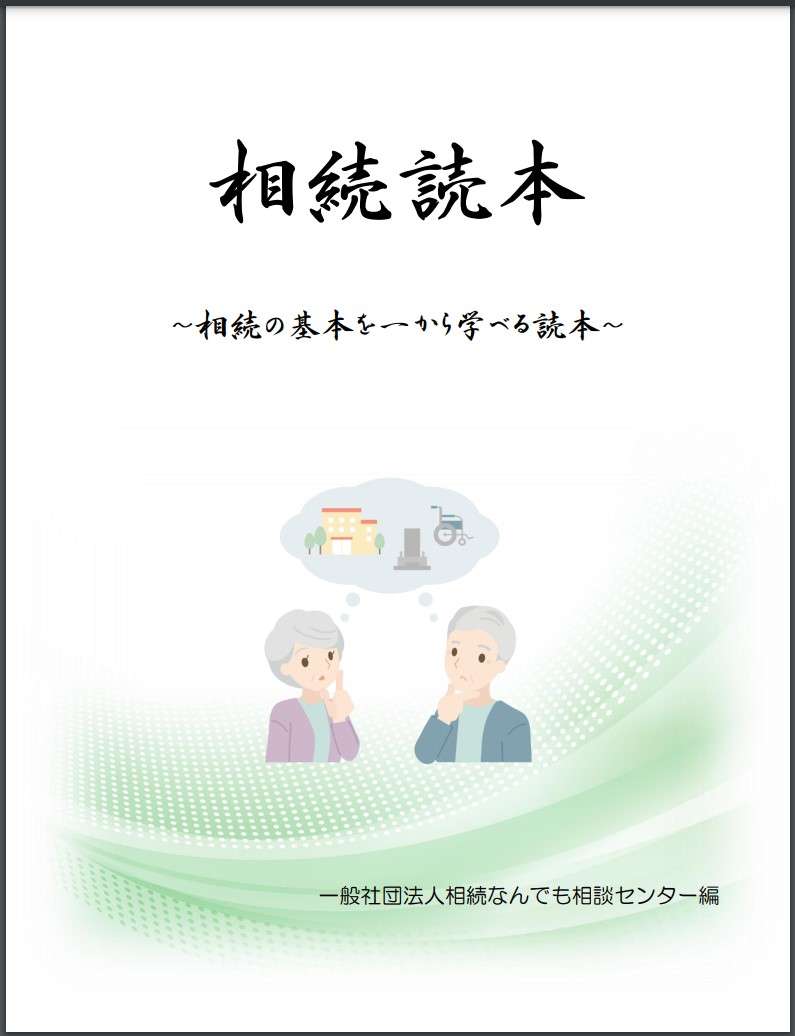【相続】遺留分が侵害された場合と遺留分の放棄
2021/07/20
目次
【遺留分侵害請求とは何か】
遺留分が侵害されている遺留分権利者は、遺留分を侵害する者(被相続人から遺贈から贈与を受けた者)に対し、自らの遺留分を保護するため、遺留分の侵害に相当する金額の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害請求といいます。
かつては「遺留分減殺請求権」と呼ばれており、遺留分権利者の遺留分を保護するのに必要な範囲で、遺留分を保護するのに必要な範囲で、遺留分を侵害する遺贈や贈与の効力を否定し、遺贈や贈与の対象となった財産自体の返還請求を認める制度でした。しかし、2018年の相続法改正(2019年7月1日施行)により、財産自体の返還請求を否定し、金銭の支払いを求めることだけを認める制度に変更されている点に注意を要します。
遺留分侵害額請求は、訴訟を提起しなくても、遺留分を侵害する者に対し、遺留分侵害請求権を行使することを明示して請求することが可能ですが、最終的には訴訟を提起して争うことになります。
【遺留分侵害請求は遺贈から行使する】
民法では、遺留分侵害請求について、被相続人による遺贈や贈与のうち、遺贈を受けた者から先に、遺留分侵害請求に応じなければならないと定めています。遺贈が複数ある場合は、遺贈も価額の割合に応じて、遺贈を受けた人が、遺留分侵害相当額の支払義務を負うことになります。
そして、遺贈を受けた者のみを対象に遺留分侵害額請求権を行使しても、遺留分権利者の遺留分の保護に不十分であるときは、被相続人から贈与を受けた人も含めて、遺留分侵害請求を行い、遺留分侵害相当額の金銭の支払いを請求します。ただし、贈与を受けた人が複数ある場合は、相続開始時から力い時期に行われた新しい贈与(後の贈与)から順番に、遺留分の侵害が解消されるまで、古い贈与へとさかのぼる形で、遺留分侵害額請求をしていくことになります。
遺留分侵害額請求権の行使については、「遺贈⇒贈与」という順番があることと、贈与が複数ある時は、「後の贈与」から順番に行うことがポイントです。
【行使期間は原則1年である】
遺留分侵害請求権は、いつまでも行使できるわけではなく、遺留分権利者が、相続開始の事実に加えて、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったという事実も知った時から1年間行使しなければ、時効により消滅します。
さらに、相続開始の時から10年を経過したときは、上記の事実を知らなくても、遺留分侵害請求権は同じように消滅します。遺留分侵害請求をする場合は、期間制限に注意しなければなりません。
【遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要】
遺留分権利者は、遺留分の放棄をすることができます。遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはなりませんので、相続人の地位は失われません。ただし、遺留分を放棄する時期によって手続きが異なることに注意を要します。
まず、相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。相続開始前に、あらかじめ相続を放棄することはできませんが、遺留分を放棄することは可能です。しかし、事業を承継する相続人などから、遺留分権利者が遺留分の放棄をするようプレッシャーをかけられるおそれがあるので、家庭裁判所の許可を条件とすることで、家庭裁判所にチェック機能を与えています。
これに対し、相続開始後に遺留分を放棄することは、遺留分権利者の自由ですから、家庭裁判所の許可なども不要です。
【遺留分権の行使についての改正の意義】
2018年の相続法改正により、かつての遺留分減殺請求権が「遺留分侵害請求権」へと名称が変更されましたが、両者の制度の間には、名称の変更以上に大きな違いがあります。
かつての遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を保護するのに必要な範囲で、遺贈や贈与の効力が否定されていました。これによって、遺留分権利者には、遺贈や贈与が行われた財産自体の返還請求が認められ、返還請求が行われた財産については、遺留分権利者と遺贈や贈与を受けた相続人などとの間で共有状態になることが少なからずありました。
このような取扱いに対しては、相続を原因とする事業承継の場面などで大きな負担になると批判されていました。
そこで、遺留分侵害請求の制度では、遺留分権利者には侵害された遺留分に相当する金銭債権(金銭の支払いを請求できる権利のこと)だけが認められることにして、遺留分権利者による財産自体の返還請求を否定しました。
たとえば、被相続人(父)には相続人として子A・Bがいるとします。被相続人が亡くなる前に、自分の事業の後継者として子Aを指名して、将来、被相続人の遺産になるはずであった、全財産である6000万円相当の事業用財産を子Aに贈与していたとします。
2018年の相続法改正により、遺留分侵害請求権に変更になったことで、子Bが遺留分侵害請求をしても、事業用財産が子A・Bの共有状態とはならず、子Aは事業財産の単独所有者として、そのまま事業を継続することができます。一方、遺留分侵害額請求をした子Bは、子Aに対して、自らの遺留分の侵害に相当する金額である1500万円の金銭債権を取得することになります。
なお、遺留分侵害請求権を受けた子Aのような人の負担を考慮し、全部あるいは一部の金銭の支払いについて、裁判所が相当の期限を与えることができます。
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!
相続についてより詳しく学びたい方
この「相続読本」は相続なんでも相談センターが長年に渡って培った相続のノウハウが詰まった1冊です。何から始めていいかわからない方、何を調べて、何を勉強すればいいのかわからないでも必ずこの1冊の中に知りたいことが詰まっています。
是非一度、手に取ってみてください。こちらのページからダウンロードできます。